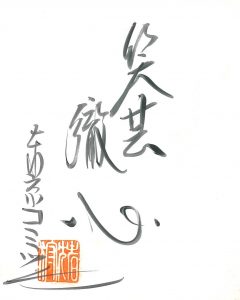東京コミックショウ~第2回 女子プロレスを始めるまで
東京コミックショウ~第2回 女子プロレスを始めるまで
女子プロレスを始めるまで
ショパン猪狩、本名、猪狩誠二郎は東京都目黒区に宮大工の五男として1929年(昭和4年)に生まれる。この年は巳年。生まれた時からヘビに縁があった。13歳年上の長兄、登がのちのパン猪狩。3歳年下の妹が定子。二番目と四番目の兄も一時、芸能活動をしていた。棟梁だった父親は職人を何人も使って羽振りがよく、常に大酒を飲んでいた。しかし戦時色が濃くなるにつれ、仕事はなくなり、酒におぼれて暴れてばかり。自然と兄たちは家に居つかなくなった。
ショパンは子どもの頃から工夫をすることにたけていた。小学生の時、小遣い稼ぎに納豆売りとなり、5センチ四方の手作りの日の丸を納豆のワラにはさんで「日の丸納豆」の名で売り歩く。愛国心が尊ばれる時代だったので飛ぶように売れた。働く楽しさを覚え、中学には進学しなかった。軍事用の飛行場を東京湾に造成していた東京京浜運河株式会社に就職するが、日本兵が捕虜をいじめるのを見て、「こんな腐った戦争には関わりたくない」と退職する。
終戦後の16、17歳の頃、パンに誘われ、定子と一緒に常磐楽団に入る。コントと音楽劇を演じる劇団で、東北や北海道を旅まわりして過ごした。芸名はパンの弟なので「小さいパン」という意味で「コパン」、それがなまって「ショパン」となった。
その後、パンはジャズに乗せてボクシングとレスリングをコミカルに演じる「パン・スポーツ・ショー」を考案し、パン、ショパン、定子の3人で進駐軍のキャンプをまわった。ショパンがレフェリーになり、パンと定子がボクシングをする。それが喧嘩になり、レスリングに変わるという内容だ。
パンさんのこの発想は、当時の日本人の笑いに対するセンスをはるかに越えていた。日本のレビューやコントが、どうしてもニワカの伝統から抜け出せなかったとき、パンさんは、満州や上海租界で見た外人のコミックチームの洗練されたスピーディなステージングに影響され、それを目指そうとしていた。たぶん、向こうで見たものをそのままパクッて作ったのだろう。でも日本の土壌に移すときに、安易な妥協をしようとせず、どこまでも自分の理想とするショーを築こうとしたところは、芸人とすれば立派だった。そして自然と俺がめざそうとしたのも、伝統や格式に縛られることのない、独自の芸をつくりあげるということだった。
『レッドスネークCOME ON!』
この姿勢をパンもショパンも生涯貫くこととなる。
「パン・スポーツ・ショー」は興行場所と出演人数によって工夫を加え、女性だけのバンド演奏を入れたりもした。さらに女子レスリングも手掛ける。力道山によってレスリングが広く知られるようになる前のことであり、日本ではまだ女子プロレスは行われていない。定子は日本初の女子プロレスラーとなった。アクロバットの芸人だった田山勝美やストリッパーだった女性を誘って試合ができる体制を整えた。試合は相手選手の腿にはめてあるガーターベルトをはずした方が勝ちというガーター取りマッチという形を取った。女子レスリングの前座試合として日本人の柔道家と外国人のボクサーが戦う柔拳試合も行った。のちにプロレスのレフェリーとして活躍したユセフ・トルコも外国人ボクサーの中にいた。
彼らの役目は、最初悪賢いことをして日本人をいじめ、最後に日本人の正義の技にあえなくやぶれること。
試合は、とにかく最後に日本が勝てばよかった。
一度、外人に勝たせたことがあったが、物が飛んできてあぶなくてしょうがない。『レッドスネークCOME ON!』
女子プロレスも本気になり過ぎてけがをしたり、疲労がたまったりしないように、派手に見せる技や演出を研究した。選手もレフェリーも芝居心が必要で、特にレフェリーは間抜けな道化役に徹する必要があった。タッグマッチでは、戦っていないもう一人ずつがレフェリーの目を盗んで、あれこれ画策するが、それにまったく気づかないふりをして客をじらす。こうした演出はその後のプロレスでもよく行われている。また、悪党と思える選手が実は善玉で、かわいい顔をした選手が最も悪党だったりする演出も行った。当時のレスリングは曲芸や曲技、奇術などと一緒に興行することが多く、ショーとしてとらえられていた。
しかし人気が高まるにつれ、真剣勝負を望む声が多くなる。興行師も収益のために無謀な興行を行い、トラブルが続いた。勝敗よりも演出を重視していたショパンたちは次第に女子プロレスから手を引くようになる。定子も観客の思いを満たすことができないことを実感して1959年(昭和34年)にプロレスラーを引退し、芸人に専念する。
←第1回
ショパン猪狩、本名、猪狩誠二郎は東京都目黒区に宮大工の五男として1929年(昭和4年)に生まれる。この年は巳年。生まれた時からヘビに縁があった。13歳年上の長兄、登がのちのパン猪狩。3歳年下の妹が定子。二番目と四番目の兄も一時、芸能活動をしていた。棟梁だった父親は職人を何人も使って羽振りがよく、常に大酒を飲んでいた。しかし戦時色が濃くなるにつれ、仕事はなくなり、酒におぼれて暴れてばかり。自然と兄たちは家に居つかなくなった。
ショパンは子どもの頃から工夫をすることにたけていた。小学生の時、小遣い稼ぎに納豆売りとなり、5センチ四方の手作りの日の丸を納豆のワラにはさんで「日の丸納豆」の名で売り歩く。愛国心が尊ばれる時代だったので飛ぶように売れた。働く楽しさを覚え、中学には進学しなかった。軍事用の飛行場を東京湾に造成していた東京京浜運河株式会社に就職するが、日本兵が捕虜をいじめるのを見て、「こんな腐った戦争には関わりたくない」と退職する。
終戦後の16、17歳の頃、パンに誘われ、定子と一緒に常磐楽団に入る。コントと音楽劇を演じる劇団で、東北や北海道を旅まわりして過ごした。芸名はパンの弟なので「小さいパン」という意味で「コパン」、それがなまって「ショパン」となった。
その後、パンはジャズに乗せてボクシングとレスリングをコミカルに演じる「パン・スポーツ・ショー」を考案し、パン、ショパン、定子の3人で進駐軍のキャンプをまわった。ショパンがレフェリーになり、パンと定子がボクシングをする。それが喧嘩になり、レスリングに変わるという内容だ。
パンさんのこの発想は、当時の日本人の笑いに対するセンスをはるかに越えていた。日本のレビューやコントが、どうしてもニワカの伝統から抜け出せなかったとき、パンさんは、満州や上海租界で見た外人のコミックチームの洗練されたスピーディなステージングに影響され、それを目指そうとしていた。たぶん、向こうで見たものをそのままパクッて作ったのだろう。でも日本の土壌に移すときに、安易な妥協をしようとせず、どこまでも自分の理想とするショーを築こうとしたところは、芸人とすれば立派だった。そして自然と俺がめざそうとしたのも、伝統や格式に縛られることのない、独自の芸をつくりあげるということだった。
『レッドスネークCOME ON!』
この姿勢をパンもショパンも生涯貫くこととなる。
「パン・スポーツ・ショー」は興行場所と出演人数によって工夫を加え、女性だけのバンド演奏を入れたりもした。さらに女子レスリングも手掛ける。力道山によってレスリングが広く知られるようになる前のことであり、日本ではまだ女子プロレスは行われていない。定子は日本初の女子プロレスラーとなった。アクロバットの芸人だった田山勝美やストリッパーだった女性を誘って試合ができる体制を整えた。試合は相手選手の腿にはめてあるガーターベルトをはずした方が勝ちというガーター取りマッチという形を取った。女子レスリングの前座試合として日本人の柔道家と外国人のボクサーが戦う柔拳試合も行った。のちにプロレスのレフェリーとして活躍したユセフ・トルコも外国人ボクサーの中にいた。
彼らの役目は、最初悪賢いことをして日本人をいじめ、最後に日本人の正義の技にあえなくやぶれること。
試合は、とにかく最後に日本が勝てばよかった。
一度、外人に勝たせたことがあったが、物が飛んできてあぶなくてしょうがない。『レッドスネークCOME ON!』
女子プロレスも本気になり過ぎてけがをしたり、疲労がたまったりしないように、派手に見せる技や演出を研究した。選手もレフェリーも芝居心が必要で、特にレフェリーは間抜けな道化役に徹する必要があった。タッグマッチでは、戦っていないもう一人ずつがレフェリーの目を盗んで、あれこれ画策するが、それにまったく気づかないふりをして客をじらす。こうした演出はその後のプロレスでもよく行われている。また、悪党と思える選手が実は善玉で、かわいい顔をした選手が最も悪党だったりする演出も行った。当時のレスリングは曲芸や曲技、奇術などと一緒に興行することが多く、ショーとしてとらえられていた。
しかし人気が高まるにつれ、真剣勝負を望む声が多くなる。興行師も収益のために無謀な興行を行い、トラブルが続いた。勝敗よりも演出を重視していたショパンたちは次第に女子プロレスから手を引くようになる。定子も観客の思いを満たすことができないことを実感して1959年(昭和34年)にプロレスラーを引退し、芸人に専念する。
←第1回
第3回→